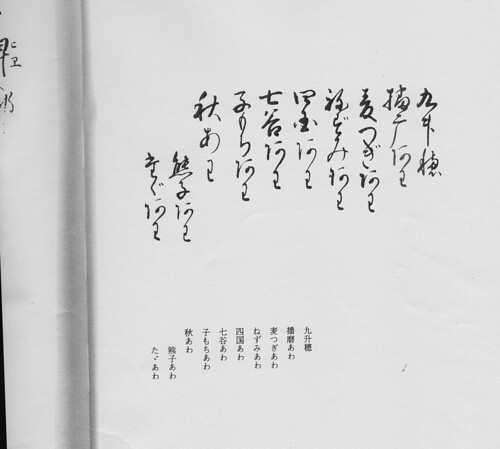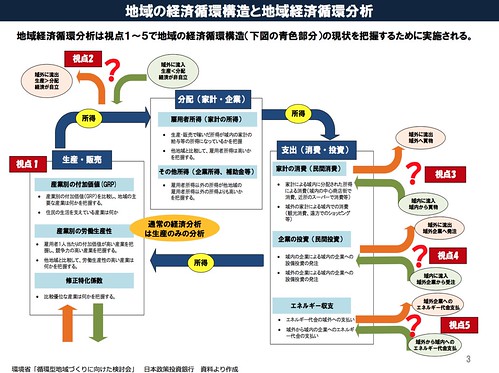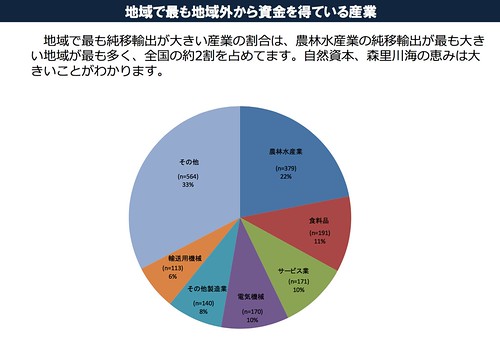昨日、6月16日のことであるが、書きとどめておくべきことして。
【ダイコン】
魚谷常吉 (著)・平野 雅章 (編)『味覚法楽』 (2003;中公文庫)
ダイコンは日本人の食物として最も広く、かつ多く用いられ、常にその恩恵に預かっているのにもかかわらず、恩に慣れてかあまり珍重がられず、その真価を認められていない傾きがあるのは、不思議といわねばならない。
(中略)
最後に、その料理法の中で特にうまいと思われる二、三について述べると、おろしダイコンをもって第一に推したい。(中略)ただ水で洗い、皮のままおろし金でおろせばよいので、そのとき汁を捨てないだけが条件で、もし水分が多すぎると思う場合にはカツオの粉を加えて加減すれば、食いやすくなり味も優れるのである。なおこれに使うしょうゆは、うま味があるものを用いるのも条件である。ぜいたくにするならば揉みノリなど加えてもよいが、そのうま味を賞するには、おろしたままの汁をしぼらないところへ、しょうゆを適宜加えるだけのものに限るようである。
『風来好日スモールライフ』の久保田昭三さんもダイコンをよく使っておられたのではと記憶する。巻頭の写真の中で畑の小さなダイコンを撮っているのだ。常食は馬鈴薯と大根と屑米と自飼いの鶏の卵であったか。そして、お元気だろうか。一筆したためてみよう。
ダイコンの民俗については、まだ最低限の整理ができていない。平凡社・世界大百科の項で飯島吉晴はこう記しているので、引っ張っておく。整理したものはひとつ前の記事に加筆する。
大根は,かつて青森県五戸地方で,10人家族でひと冬700本用意したというほど,漬物やかて飯の材料として日常の重要な食糧とされた。一方,大根 は種々の形に細工しやすく,婚礼の宴席に男女の性器を模したものが出され,またその色が神聖感を与えるために,古くから正月の歯固めをはじめ,ハレの日の食品や神供として用いられた。
追記すると、アエノコトにおいて、ひと組のダイコンを男女に模している再現写真があって、これは興味深い。これは奥能登のこととして後述されてもいる。
また大根は種々の俗信や禁忌を伴っている。種を土用の入りや丑の日に撒くと,葬式用や曲り大根になるといって 嫌う所が多い。また大根畑に七夕飾りの竹や桃の枝をさしておくと虫がつかないという所も多い。東日本では,十日夜(とおかんや)を〈大根の年取り〉といい,この日に餅をつく音やわら鉄砲の音で大根は太るといい,大根の太る音を聞くと死ぬといって大根畑へ行くことや大根を食べるのを禁じている所もある。西日本では10月の亥子に同様の伝承があり,この日に大根畑へいくと大根が腐る,太らない,裂け目ができる,疫病神がつくといい,また大根の太る音や割れる音を聞くと死ぬともいう。このほか,半夏生(はんげしよう),彼岸,社日,夷講などの季節の折り目や収穫祭にも大根畑にいくのを忌む。これは大根が神祭の重要な食品であり,大根畑は霊界に近い神の出現する神聖な場所と見なされていたことを示している。
北九州では,稲の収穫祭である霜月の丑の日の前日に大黒祭が行われ,二 股大根を箕(み)にのせ,供物をして祭っている。奥能登のアエノコトでも,二股大根を田の神として丁重に扱う風がある。大黒と大根は語音が近いためか,二股大根を〈大黒の嫁御〉といっている地方は多い。また〈違い大根〉は聖天(歓喜天)の紋とされ,この絵馬を聖天にささげ,大根を絶ち,夫婦和合や福利の祈 願を行う。また,大根が聖天の持物とされることもある。
【河内とは】
奥出雲町三沢の河内と四日市の土地の履歴をたどるにあたっての知識として備えておきたく。
大塚 英志 (編) 『柳田国男山人論集成』(2013,角川ソフィア文庫)所収
「山民の生活」(下)
p73
山々の神を本居宣長は、大山祇神であろうとか大山辺の神であろうかというけれども、そうではない。民俗にはただ山の神とのみいいならわして居る。山に向かって入るところに祀るまでの神である。荒神は原野山野の神である。
「山民の生活」(第二回大会席上にて)
p76
「山口」とか「川上」とかいう村は次の時代にはすでに川下に成ってその奥にまた村が出来る。例えば若狭の南河の谷などはほとんど源頭まで民家がありまして、「奥坂本」という村の奥になお数箇の部落があります。我々の祖先はかくのごとき地形を河内(カワチ)と名づけまた入野(イリノ)とも呼びました。「我が恋はまさかも悲し草まくら多胡の入野の奥もまかなし」という万葉の歌などは、入野が盛んに開かれた時代には人を感ぜしめた歌でありましょう。
入野では三方の山から水が流れますから、……
p88
全国を通じて最も単純でかつ最も由緒を知りにくいのは「荒神」「サイノ神」「山ノ神」であります。仏教でも神道でも相応に理由を付けて我領分へ引き入れようとはしますが。いまだ十分なる根拠はありませぬ。
「山ノ神」は今日でも猟夫が猟に入り木樵が伐木に入り石工が新たに山道を開く際に必ずまず祀る神で、村によってはその持山内に数十の祠がある。思うにこれは山口の神であって、祖先の日本人が自分の占有する土地といまだに占有しぬ土地との境に立てて祀ったものでありましょう。
…
荒神も三宝荒神などといって今は竈の神のように思われておりますが、地方では山神と同じく山野の神で。神道の盛んな出雲国などにも村々にたくさんあります。