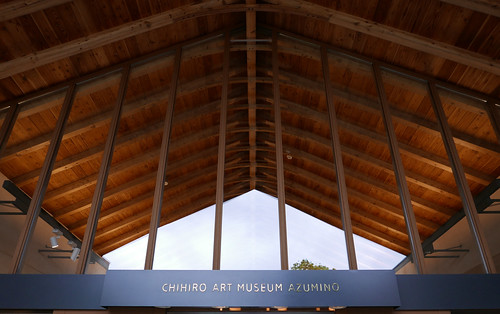本の顔の7日間、その3。
◉種村季弘『雨の日はソファで散歩』筑摩書房,2005

「書かれたものは、いわば音符に過ぎない」中井久夫)
この本は、推理小説にも似た、謎解きを誘うようなところがあって、そんな奏で方(読み方)があったのかという訪れを、静かに待っているようにも、見える。
たとえば。
「鳥目絵の世界」と題された一編。
鳥目絵、鳥瞰図をめぐるひとしきりの話の後、これでおしまいという結語のような〆につづけて、そうそう大事な話を忘れていたというように取り出される一節がある。
ドラマシリーズ「相棒」で杉下右京が、去り際「あぁ、そうそう、最後にひとつだけ」といって大事な質問をするあれのように。
種村季弘によって、それはこう切り出されているのだ。
”気になっている鳥瞰図がある。精神病理学者の中井久夫がポーの「ランダーの別荘」を、その記述通りに鳥瞰的に再現した地図である。……(略)……ポーの「ランダーの別荘」は、谷崎潤一郎「金色の死」や江戸川乱歩「パノラマ島奇談」のモデルとなった。とりわけ「パノラマ島奇談」では独裁者的人物の偽の神の目の下でパノラマ化した島が果ては大花火とともに空無として消え去ってしまう。”
どうだろう、迷宮の入口らしきものを感じられたのであれば、この続きを、どこかで誰かと話せる日を楽しみに取り置こう。
いや、いや、その前に、手元に置かれたままの原稿を本にまとめる約束を果たさなければならない。
まち、むら、やま、そういうものを本を読むように読むことができる。「……そのノウハウを教えてくれたのは、私の先生で種村季弘という人がおりました」と語られる髙山宗東氏の一稿。
どんな絵になるかもわからないパズルのピースだけが、本の外側のほうぼうに、転がっている。それを拾ってきて、この本の中にあてはめてみるのだ。