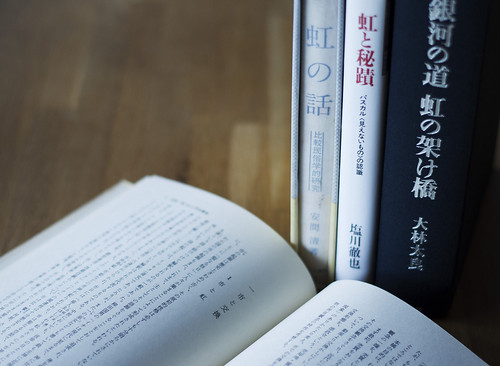7月13日であろうか。NHK総合テレビが全国ニュースである問題を報じた。「自治体が主催する夏休みの子ども向けのツアーやキャンプなどが、いま、各地で次々と中止に追い込まれています」というもの。SNSでは方方でああでもないこうでもないと、感情的祭りの状態。
以前から取沙汰されていた問題であり、とりわけ地方創生が叫ばれるようになり、イベントに公的資金や助成金が投入されることで、事情がさらにこじれてはいよう。また、この報道が、改正旅行業法の施行を控えての「バルーン」であろうことは意識して見ないと、状況認識を間違えよう。
◉参議院通過
◉閣議決定
◉検討会
あぁ、さて、しかし、こうした「祭り」は昨今とみに顕著でありことから新しい社会現象にみえるが、さにあらず。古くから繰り返される、日本の社会ならではの、長らく護持され続けている固有の性格に基づくものだと考えてみた。
そう思うに至ったのは、上にあげた旅行業法をめぐる、ああでもないこうでもないの「騒ぎ」である。旅行業法が何を規制しているのか。取り締まるのは誰なのか。そしてその法に抵触するかもしれないからと中止になる事業は、なにをめざしているものなのか。いったい何が悪いのか。どうすべきなのか。
個別具体の例はもちろんのこと、一般抽象の問題としても、騒ぎの俎上にあがってこないのだ。いったいなんなのだろう。その違和感とも焦燥ともいえるものを、少なからぬ人々が感じていたようで、「モヤモヤ」「イライラ」「カリカリ」という音がウェブの端々から漏れ聞こえてきた。
そう。社会ニュースの「いつものこと」ならば、糾弾される個人・団体が個別具体的にあるだけに、その対象を罵り、蔑むことで、溜飲をさげようとする大衆心理がわかりやすく展開されるのだが、今回はその対象があるようでない。自治体の担当部署から市民ボランティアグループあるいは親子会のようなものまで、「対象候補」だけは巷にあふれている。それぞれに千差万別、ひとつひとつ見ていけば、一括りに論じられるものではないことだけは明々白々。無理に糾弾しようとすれば返り討ちにもあいかねんような問題である。
にもかかわらず、「祭り」は作動した。馬鹿馬鹿しいくらいに。
定形が要求する収まりは記者会見の席での、ひとこと。「この度はお騒がせして申し訳ない」という謝罪の言葉である。今回の騒動は定形に収められないことによる違和を生じているが、力学は同様。この言葉、決して凡庸なる定型句だとは考えない、私は。
「この度はお騒がせして申し訳ない」
その意味するところを語る方も聞き入れるほうも深いところで理解しているのだ。
どういうことか。
「騒がせた」ことが悪いのであって、騒ぎの原因たる行為の善悪には言及していないのだ。「私が悪かった」と言っているのではないし、糾弾するほうとてそれを求めていない。儀式として、対象者が「非」を詫び、糾弾者は儀式として「非」を攻めるのだから、あたかも容疑者=犯人であるかのような錯覚を生じさせる構図に対して、それはおかしいという向きもあろう。
だが、注意深く観察すればわかるだろう。
この劇場内にあって、行為の善悪は問われることはない。換言すれば、善悪を問うような言語文化を日本語は形成しそこねてきたのだ。明治の初頭以来。
川島武宜は、明治日本国家が創出した6つの法典、すなわち憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法を評して、短期間に驚くべき才能の結集によって作成された希有のものとしつつ、”列強と伍するために明治の法典を“日本の飾り”にするためにつくられたものと位置づけている(『日本人の法意識』。
明治より前、江戸時代に通用していた「法規範」「法意識」が明治の新法典制定以降も存続していたというようにもいえるのだが、いまは踏み込まない。ただ、では、その江戸時代にあった法規範とは何か。
尾藤正英は『江戸時代とは何か』の中で、戦国時代における喧嘩両成敗法を、いわゆる「法」ではないものとして、こう論じている。
《裁判権を集中・独占するということの意味は、本来はこのように理非を判断する権限を掌握することを指すのではあるまいか。しかし戦国大名による裁判権の集中は、そのような内実をともなわず、むしろ権力者としての主体的判断を回避したといわれても仕方のないような両成敗法の採用という形をとった。その事実は、大名といえども、一揆など各種の自生的な集団のなかで、明文化されると否とを問わず、形成されていた慣習法的な規範から自由ではなかったことを物語っているのであろう》
そして、尾藤の論は、この慣習法的規範の優越が江戸時代を通して貫徹されているのではないかとう驚くべき展開に進む。そしてこう結論づける。
《あらためて考え直してみると、法的な規範として幕藩体制を支えていたものは、じつは慣習法の巨大な体系的集成であったといえるのではあるまいか》
……つづく。