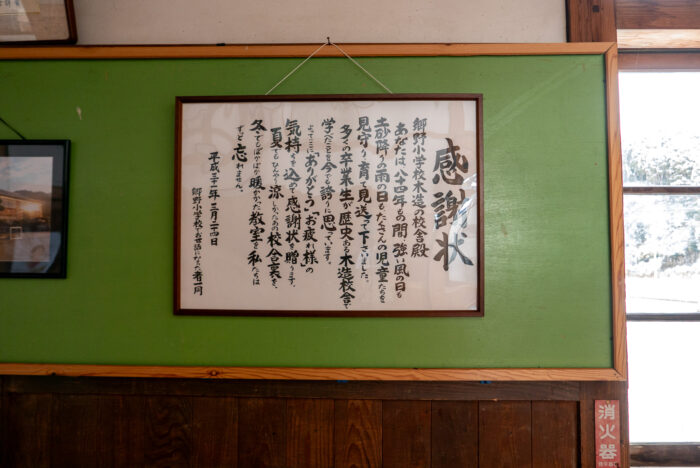令和7年3月31日の午後であった。お天気もよく、疲れもたまっていたので、妻とふたり、それぞれの仕事の合間を縫うように、近所の秋葉山へ。
そこで、昭和14年生まれの86歳だというご老人とお話した。以下、その備忘である。
昨日は雪が降っていたことを思い出させるほどに風は冷たかったが、まだ葉に遮られることのない陽射しが、強く暖かく樹下に届いていた。
小綺麗に服を着合わせ、ステッキを手にされた老紳士は風景に溶け込んでいた。頭上の桜を仰ぎ見るその視線は、やがて遠くの山々へそして眼下の町並みに、あるいはまた一本の大きな桜の樹にと、泳ぎ遊んでおろられるようにみえる。山上にはわたしたち3人のほか人影はなく、向かう方向も同じであったので、先に向こうから自然と声をかけられた。
「ここの竹藪もずいぶんとひろがって。前は向こうまで景色がのぞめたものだったが」と。
「そうですか。私たちはこちらへ越してきて十数年しかないので、この竹林の景色しか知らないのです。その昔にはなかったのですね」
木次の町で生まれ育ってこられた方であった。春にはいつもここの桜を見にあがるのだという。別れてからも、妻といろいろ話したことなど、忘れてしまうのが惜しく、思い出すための箇条書きをここに。
◆花見は家族でするものだった。それがだんだんと職場や団体でするものにかわっていった。訪れる人もにわかに増えた。
◆木次の桜といえば、この山の桜のことだった。あまりに花見の人が増えすぎてしまったため、土手の桜のほうへ人を仕向けることがはじまって、今に至る。
◆今年の桜はおかしい。開花の時期が木によって違いすぎる。こんなことは今までなかった。
◆昔のことをみな語らなくなった。なぜだろうと不思議に思う。昔より今のほうが大事だというのはわかるが、その今とはそんなにいいものだろうか。
◆町から人がいなくなった。桜がこんなに咲き始めているのにだれも歩いていない。仕事があるからだろうが、仕事がなによりも大事な社会になってしまった。
「ねえ、まだ先だと思うかもしれないけど、すぐ先、あっという間だよ。考えてみてごらん」
「ほんとだ。ちゃんと生きなきゃね」