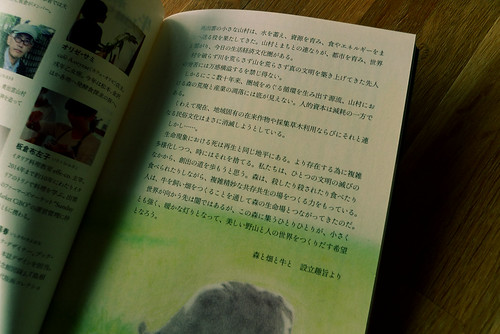記録が残せていない。 2018/05/27時点。 春の火入れ準備へ向けて、7〜10回の活動日を経過したところで、ざっくりと、遺漏もあること前提で、ほんとうにざっくりと記しておこう。
◆2017年の夏焼地あとの状況
・蕎麦も温海カブも成育はよくなかった。土質、地形、気候、種子、など各種要因と相互連関の複雑さからいって、「原因」たるものを記しがたい。どれも、『栽培」にとってよいとはいいがたいものがあるという点はあった。
・カブは種取りのために残してある。蕎麦の跡地を中心に古代小麦を11月ごろ撒種して、発芽そのものはよかった。春からの成育が遅かったのは山地特有のものだとしても、春先に鹿(だろうと思われる)の食害にあい、その後の乾燥もあって、枯れてしまうような区画が3〜4割あった。
・そして、昨日、5月26日の写真を下にあげる。
◉温海カブの春
小鳥、おそらくスズメではないか。ほとんどの実が食べられてしまった。
5月16日の状況がこうであった。

ここから10日が経過していたわけで、そりゃ間があきすぎていた。枯れるのも早い。一昨年は6月の上旬に種取りをしていたから、遅すぎるというわけでもない。平地では時期としてはまだ少し早いくらいだから。ただ、もともと食害にあっているということ、そして水持ちが悪い場所にあった(馬の背部分)ということ、今年は植物の開花・結実が平年より2週間あまり早いということを考えれば、もっと早くに動いていれば、ここまでひどいことにはならなかったろう。
やむを得ない。一昨年の種が若干残っている。発芽率は落ちているだろうが、それらを撒くことと、保険として昨年購入しておいた温海カブの種子を今年は使う。
◉古代小麦の春
こういう状況だ。
出穂も得られた。問題はここから先。少なくとも鳥には食われないように、開花後2週間後くらいには防鳥の網をかぶせることとする。 きびしいなかでのかすかな希望でもある。カブも蕎麦もダメであったし、鳥からも獣からも食われていまうという状況のなかで、どういう結果が得られるか、もう少しだけねばってみたい。