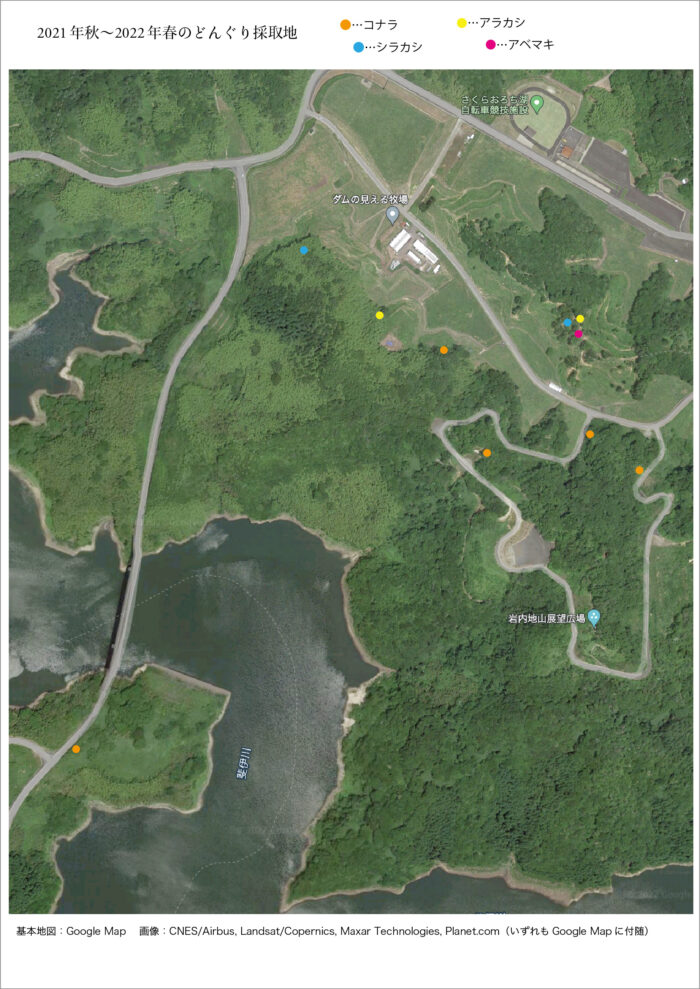クサギ。シソ科の低木で、夏に咲く花は、ジャスミンに似た香りを漂わせる。草木染めではおなじみの植物であって、青がとれるのは藍とこのクサギだけだ。珍しい植物ではないが、そうひんぱんに見かけるものでもない。そのクサギ。焼畑をしている奥出雲町佐白のダムの見える牧場内で、最近多く見かけるようになった。いくつか思いあたる節はあるものの、なぜかはよくわからない。ただ、ほんとうに、あそこにも、ここにも、というようにどこにでもある。成育も早く、あっという間にいちばん目立つ樹になってきた。仕事の手を休め眺めていると、思うのである。食えたらいいのになあと。人として自然な感性の発露ではあろう。
そして、食えるのだ、実際。食えるということはわかっている。問題はいかにして食うか、である。
同時に気になることがあった。紙とウェブを問わず、やたらと「臭いからクサギ」「悪臭」「なんでも食べるウサギもこの木だけは食べない」という記述が並びたっている。おそらく、食べたことも、嗅いだこともんなく、どこかで書かれたものをそのまま写してしまうからであろう。それら記事のなかでも、実際、食べたことのある人は「それほど強い臭いではないし、もっと臭い木はある」というトーンとなる。
私も、最初はおそるおそるちぎって嗅いでみたものだが、独特の香りはあるものの、悪臭であるとは全く、本当に全く思わなかった。件の記述を拾うなか、理由として次のことを考えた。
1. 臭いに対する個人差……いやがる人とそうでない人がいる。どんなものもそうだろうし、あるだろう。
2. 季節による……山菜としてとるのは6月までのようだ。夏・秋には臭いがきつくなるのかもしれない。私も夏・秋にはちぎっていないので、確かめてみよう。
3. 煮るときには匂う……実は2日ほど前に試してみた。臭いはしますが、臭いとはとうてい言えない。むしろ好感。どこかで嗅いだことがあるなあと。シソ科ゆえに、赤しそに似ている気がする。
4. 昔ほど匂わなくなっている!……及川ひろみさんのコラムで言及されている。cf.《宍塚の里山》49 美しい花を咲かせる「クサギ」は臭いか
それはさておき、食うために、である。
出雲圏域で郷土食資料をざっくり縦覧した限りでは、奥出雲の横田地区にみられる程度であるが、県境をまたげば、広島県岡山県の山間部には食習の残るところも多い。道の駅でふつうに売られているらしいとも。確かめる機会は夏にと思う。食欲増進にいいようで、夏バテ解消にもなるかもしれん。
採取の仕方、調製の仕方に、さほど大差はない……ともいえるが、「10時間ゆでる」から「さっとゆでる」までの幅はある。そのあたり捨象しながら、以下のように採取と調製をまとめた。
1. 採取時期は5月〜6月。6月に採るというところも多い。とりやすいのは6月に入って大きく葉が展開している時期だろう。5月では小さい。葉は卵の大きさくらいとも、もう少し大きなものとも。今回はバラバラの大きさで採った。葉が大きすぎると食すときに、くだきにくいのではないか、あるいは煮沸の時間がより長くなるのではないか。一方で小さすぎると、味や香りが薄くなることもあるだろう。
2. 調製は、採ったその日に煮沸すること30分。その後一晩おいて、水でさらして、日干しする。6月後半の暑い日であれば、1日でパリパリに乾く。灰や重曹を加えて煮た方がよかったのか、まずはそこが試される調理編は、近日実施予定。