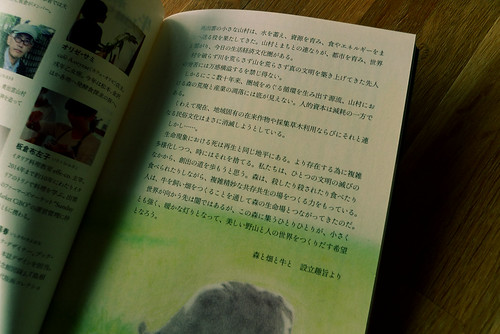奥出雲の小さな山村は、水を蓄え、資源を育み、食やエネルギーをまちへ送る役を果たしてきた。山村とまちとの連なりが、都市を育み、世界と繋がり、今日の生活経済文化圏がある。
村を破らず川を荒らさず山を荒らさず真の文明を築き上げてきた先人の労苦には万感横溢するを禁じ得ない。
しかるにここ数十年来、圏域をめぐる循環を生み出す源流、山村における森の荒廃と産業の凋落には底が見えない。人的資本は減耗の一方である。
くわえて現在、地域固有の在来作物や採集草木利用ならびにそれと連なる民俗文化はまさに消滅しようとしている。
しかし……。
生命現象における死は再生と同じ地平にある。より存在する為に複雑多様化しつつ、時にはそれを捨てる。私たちは、ひとつの文明の滅びのなかから、創出の道を歩もうと思う。森は、殺したり殺されたり食べたり食べられたりしながら、複雑精妙な共存共生の場をつくる力をもっている。人は、牛を飼い畑をつくることを通して森の生命場とつながってきたのだ。
世界が向かう先は闇ではあるが、この森に集うひとりひとりが、小さくとも強く、暖かな灯りとなって、美しい野山と人の世界をつくりだす希望となろう。
森のこと山のこと
焼畑の終わりと始まり

日本における焼畑は稲作以前、縄文時代から行われていた可能性が唱えられてきた。空間的にも北海道から八重山諸島にまで広がっている。その形態や特質は多くの変貌を時間的にも空間的にもとげながら、野山に火をいれるというその一点は近代まで連綿と続けられてきたことに間違いはない。
少なくとも数千年におよぶ焼畑という営みも、昭和三十年代に入り急速に衰退し、確実に終焉を迎えたと、野本寛一は言う。現在の80代世代が、その最期を見届けたことになり、私たちにその探求の道は閉ざされた。
一方で、平成も終わろうとするこの時代に、焼畑の火は消えそうで消えず、もはや歴史の進みの淀みとはいえないだろう。むしろ、数千年のときをへて、やっと、私たちは焼畑の真実にたどりつけるのかもしれない。黄昏に飛び立つミネルヴァの梟をとらえるがごとく。
繰り返し同じようなことを言う。焼畑のイメージはつねに焼畑そのものから遠ざかろうとする。裏切り、間違い、幻像。「灰が肥料になるのですか」「究極の循環農法ですね」「環境破壊では」……すべてイエスでありノーである。
奥出雲・佐白の地で「焼畑」を試行して三年。焼畑は農法や伝統や文化というよりは、生命現象に近いなにかであると予感する。
焼畑は通常、Slash and burnで通用するが、Shifting cultivationも捨てがたい通念だ。むしろ「移動」することが「焼く」ことよりも本質をついているだろう。通説では、焼畑が場所を移動=Shiftingするのは、地力の衰えあるいは除草の手間が増大するためだとされる。が、本当にそうなのだろうか。
別な言い方をしてみよう。焼畑が移動をその核にすえるのは、管理から逃れるためであり、定住と集団の大規模化に抗するためであると。anti-cultivation、すなわち反文化としての焼畑。
山の利用をめぐって、明治政府はまず自由放牧を、つぎに焼畑をしめだした。間接的にではあるが。抑圧する側としては、制御したいのであって、抑圧そのものが目的ではない。
反文化は、文化に抗するわけだが、それは文化の側からの視点であることをことわっておく。
野山に管理を徹底することで、結果としてなにが起こったのか。国は富を拡大できただろうか。人は豊かさを享受できただろうか。幼子を飢えや病気でなくす悲しみを総体として減らすことができただろうか。これもイエスでありノーである。
「森が荒れ」「鳥がいなくなり」「山にはもう入れない」と土地の老人たちはいう。
嘆きだろうか。いやそうではない。これは託されているのだ、まだ動ける私たちに。
もうやらなくてもいいのだと。
だが、やるなではなく、やってもいいというメッセージがそこにはある。
やるなら覚悟をもっておやりなさいよ。そうやさしくはいわないだけであって。
そう勝手に受け取って、私たちははじめたのだ。
荒れた森を切り開き、火を入れ、畑をつくる。花が咲き、虫が集まり、鳥が少しずつふえ、荒地のキク科雑草の繁茂も二年目でずいぶんとおさまり、見ることのなかったスミレや柔らかな草、眠っていたチャノキが背をのばしはじめている。新しい森が成熟するにつれて、これらの生命はまた次第に消えていくだろう。
作物の種はあつくまき、その多くは死に、生き残りもどんどん間引いていく。それでもできたりできなかったりする。
まあ、なんとかつくりたいという一心なのだが、生と死が等価であるような生命の流れに同化することでなんとか私も生きたいと願う。
「山をする」牛
◉「山をする」
「放牧することをわが地方では『山をする』といいました」
佐藤忠吉は『自主独立農民という仕事』(森まゆみ著・バジリコ刊)のなかでそういう。昔というのがいつのころからなのかはわからない。皇国地誌に残る牛馬の頭数や昭和30年代まではいくばくかの古態を残していたであろう民俗の記録などから、少なくとも江戸時代中期からの姿であるならば大変おぼろなものではあるが想定はできる。つい60年ほど前まで、「山をする」という言葉は生きていた。
また区域を出雲にとどまらず同類の地勢や集落形態、経済圏ともいえる鳥取県・岡山県・広島県の中国山地地帯にひろげれば、奈良時代からつづく牛馬放牧地帯であることは確かである。日本における牛馬を飼養した起源については考古学的知見がわずかにあるばかりであり、定説らしきものも不確かなようである。
そもそもが、これ、牛馬放牧に対する国民的「無関心」に起因するようだ。稲作の起源、あるいは縄文・弥生の土器などわかりやすい形のみえるものについては、その時代を証するごく一部の断片であるのにもかかわらず、その断片から全体像をむやみに描こうとするがゆえのゆがみがあるように、このごろ思えてならない。
同じ轍をふむことをおそれつつ、わからなくなった「牛をする」ことについて、想起をめぐらしてみよう。
牛を山に放つことは、私たちがイメージする放牧とは違うなにかであったことは、言葉そのものからもうかがえる。
私たちの頭は、牛を飼うことを、目的別にわけて分類して事足りることに、あまりにもなれすぎてしまった。
牛乳(生乳)生産のための乳牛。肉にするための肉牛。このふたつのいずれかであって、古来日本の和牛は食用ではなく乳をしぼることもなかったがゆえに「役牛」と一括されていることにもよくあらわれている。
死んだ牛はすべてではないにせよ、肉として食されていた。建前として禁じられていたがために記録に残っていないだけである。また乳を飲むこともあったらしいが、基本は小牛のためのものであった。あたりまえといえばあたりまえだが。
そして、つい数十年あるいは現在でも牛を飼う家々のその「目的」を私たちは忘れている。いわゆるペットである。とりわけ江戸時代後期から昭和の戦後まもなくのころまでにおいて、ここ奥出雲をはじめ、鳥取、岡山、広島の山間部において牛の放牧頭数は全国屈指のものであった。しかもどの農家も一頭から数頭までの小規模でありながら、共有山野での放牧や平地への貸出(鞍下牛とこの地方では呼んでいた)といったリースもあれば、権利のやりとり、保険・金融機能との融合、市場取引などの重層的利用もからんだ、文字通りの資本財(cattle〜capital)であったのだが。。。
だが。個々の家々の動機は、使役とともに糞の堆肥利用という合理的目的はあったにしても、女性や子供の「愛玩動物」としての価値と効果を低く見積もりすぎてはいなかったろうか。
民俗資料ではない、老人倶楽部がまとめた「言い伝え」のような文集のなかにあらわれる、牛を飼っていたときの綴りには、牛といかに情を交わしていたか、その気持がにじみでているのだ。鞍下に出すときには、からだをきれいにふき、藁をあんだ沓をはかせ、前の日からごちそう(おからや大豆をしぼった呉汁)をとらせ、見えなくなるまで手をふって見送る。
帰ってきたら必ず痩せていてかわいそうだったというその心はやはりこの国ならではのものであったことだろう。
少なくとも多頭飼育をし、肉を食べる国の牛飼いの話を伝えきくに、情が移らないような飼い方をするのだという。裏をかえせば、日本においては情が移ってもよいとしていたしその利点のほうをたかくみていた可能性は高い。
寡頭飼育であるがゆえの必然でもあろうが、「山をする」といったときのような、他のあり方とのインタラクションのよさがあったのではなかろうか。具体的にはまだみえない。
物乞いと神人と森人〜雑考:わからないものへ向かう仕方
私たちはいつの頃からか、日々の暮らしのなかにあった、繊細な思考を失った。それがどんなものであったかさえ、想像はおろか妄想すらできはしない。これは悲嘆ではない。希望をもたないところから見える光であるならば、あるいは真実のかけらなりとも、落としてくれるかもしれない。
私は何を繊細な思考と呼ぼうとしているのか。どのような思考が繊細さと結びつくのか。浮かんでは消えていくイメージの連鎖に頼っている思考をそう呼ぶだけではないのか……。
繊細な感受性、ではない、繊細な思考。
たとえば、次の一文をよんだとき、あぁ、これは感性というよりは思考だ、と、思った。
《そして実践家であった。……(中略)……(乳牛の)搾乳が終わって夜遅く二時や三時になっても、車をとばして村の病人の相談にのる、悩む人の相談にのる。しかも生まれたときの姿のまま、自分を自分以上に大きく見せようともしない、小さくも見せない。……(中略)……大坂君の「牛が落ちつかないのは化学肥料を使う田の畦の草を食べているのが原因ではないですか」という言葉は大変なヒントになりました。硝酸塩中毒になっているというわけです。それほど彼は感性のよい、感受性のつよい男で、一九六五(昭和四十)年、隣りの農家の農薬によって汚染された田の畦の草を牛に与えたところ、瞳孔の異常、視野狭窄が起こることに気がついて私に教えてくれた。》
(森まゆみ,2007『自主独立農民という仕事』)
まとまらない迷想のなかで、藁をつかむような感はあるが、こう言ってみる。
「わからないもの」を考え、とらえようとするときに、思考は繊細なものとなる。
ここから、はじめてみようと思い立った。
先の大坂君は、繊細というより科学的なのでは? そう思う人もいるだろうし、無理もないのだが、それは科学の本質に対する誤解に起因する。科学の思考は繊細なものなのだ。
記事カテゴリの中で、「ホトホト・カラサデ」に入れている一連のもののなかに、それはたちあらわれる。
あるいは、「岩伏の谷の森神」でふれようとしているものに、それはある。
荒神も石神も森神も、果たしてなんであったかについて、知ることは不可能であると、すでに何十年も前に柳田國男が記している。
私たちの時代には、「わかる」ことが当たり前となった世界である。
わからないことも、わかる人から教えてもらえれば、わかったことになってしまう時代。「わかる」こと、それは人であれウェブであれ、情報のデータベースとして存在し、その場所から「ダウンロード=複写」してくることでしかない。
そのような知とは異なる相貌をもっているのが、凋落と落日を嘆かれている日本の民俗学である。
河出文庫の宮本常一『生きていく民俗』。その解説を「無数の風景」と題して寄せている鶴見太郎は、こうときはじめる。
《民俗学とはすぐれて経験的な学問である。民俗事象が無数の人間によって積み重ねられた経験の堆積である一方、民俗学に従事する側にもまた、旅先その他における無数の出会いがある。》
さて、本題はここからなのだが、もはや夜も明け方に向かいはじめた。睡魔にひとまずは降伏するとして、ここで、いくつかの断片をあわてて記し、自らの道しるべとしておく。
・経験的であるということは、国家的なものに抗する知を志向する。
・日本の乞食の源流に聖性あり。
・仏教のサンガ組織が物乞いによる組織運営を選び取ったことの後世的意義
・乞食する僧も職人も、山を拠点にした。そういう山とはなんであったのか
そして、もうひとつ、宮本常一『生きていく民俗』からの引用をもって、この記事のタイトルとの関連を示しておこう。
p.40「物乞いと商売」〜
《(白山では)山地を焼いて焼畑耕作を行なっても、そこから得られる食糧だけでは半年食いつなぐのが精いっぱいで、食物がなくなると地内子たちは椀を持って牛首まで出かけたのである。牛首の親方たちの家ではヒエの粥をたいて飢えた農民にふるまった。しかし山に仕事のある間はよいが、雪が降って仕事ができなくなると、この人たちはいよいよ窮して、山を下って平野地方に出て物乞に歩きはじめる。……(中略)……雇われて働けばよさそうなものであるが、そうする者は少なく、ただ家々の門口にたって物を乞うたのは、もともとそのまえに白山の御師または強力として働いていたころの名残であったとも考えられる。そのころは白山信仰者の家をお札配りなどして歩いて金や食物を得ていたに違いない。
……(中略)……
山奥で生活をたてることはまったく容易ではなかった。山中の者が里へ乞食に出る風習は実は白山山麓ばかりではなかった。中国地方の山中からも里の方へ乞食に出る風習があった。
……(中略)……
(中国地方ではたたら製鉄に要する膨大な炭焼き需要があったことに言及したうえで)
米をつくるだけではとうてい生活のたてようのない山中でも、こうして炭焼のもうけがあるということによって、山中にも人が住んだ。しかし炭焼で得られる金もたいしたことはないから、雪が深くて炭焼もろくにできないころには箕や簔をつくり、また篩などもつくって、春さきにになると里の村々へ売りに出たのである。なかなか器用につくってあって、里の人には喜ばれたが、だからといって、毎年買ってばかりはいられない。しかし、売りにくれば義理にでも買わなければならないとされた。また売る方も、相手はきっと買ってくれるものと信じていた。今日の商法からすると不合理なようであるが、山人は里人がその製品を買ってくれなければ生活をたてることができないので、ただ品物を買ってもらうというのでなく、助けてもらうような心持があった。だから買うことを拒否するようなことがあると、放火されたり、物をぬすまれたりする場合すらあった。》
(つづく)
摘み草の記憶〜#001
野山のものを採取し食す。この行為を促すマインドセット※1は、食文化・食習慣の変容にさらされてなお、その原基のようなものを保持するのではないか。そう推するに足るいくつかの出来事があったので、まとまりなくも綴ってみる。
かめんがら(cf.2016年のガマズミ)について、子どもの頃にはよく山で取って食べていたと、いま60代の方々から聞くことがあった。ここでいう「子どもの頃」という時代を、現在65歳の人が10歳だった頃とすると、昭和38年(1963年)のことだ。
昭和38年といえば、東京オリンピックの前年である。農村には牛に代わり、トラクターをはじめとした機械が入り、トラック輸送が食品流通をかえ、日清のチキンラーメンをはじめとした食のインスタント化が進行していた。「鉄腕アトム」の放映がはじまった年でもある。ちなみに当時にあっては原子力は未来の夢のエネルギーと見られており、資本主義を打倒し民衆を解放するものとして共産主義が推するものでもあった。 この時代、家庭で味噌をつくることが「恥ずかしい」「遅れた」ことだと見られる地域もあった。味噌や醤油は「買う」ことが進歩的だと。
小さな経済循環を解体し大きな経済循環のなかで、社会を再形成することが「是」とされた時代である。「こんにちは赤ちゃん」がヒットしていた。ベビーブームの谷間の世代でもある。

By Mc681 – 投稿者自身による作品, CC 表示-継承 4.0, Link
この項、つづく(のちに加筆)。
●2017年12月の年の瀬に、とある40代女性の会話の渦にちょっと驚いたことについて。 「今の子達でも、〇〇の実をとって食べたりするから、びっくりしたのよ。いつ覚えたんだろうと」 「へえ。そうなんだ。私たちが子どものころは、△△はよくとって食べたよね〜」 「あぁ、□□は吸うと美味しかったわ〜」
そうした行動や嗜好が発動するのは10歳前後であって、長じるに従って失せていく。ただ、いずれは消えてなくなるかもしれない。なにより、消そう消そうとする力は強く作用しているのだから。
ここで注目したいのは3つのことである。
1.民俗文化の断片が子どもたちの「遊び」の中に残存するということ……柳田國男が「小さき者の声」で言及していたように、それらは大きな変形を起こしながらも残る。柳田はそれを「大人の行為を真似する」ということに因を求めているが、《模倣》ではない何かがそうさせるのだと考えると、ひとつの理がそこに見いだせる。
2.採集草木の利用が社会の中で失せても、子どもの「おやつ」「遊び」の中に残存するということ……よくわからない。あえて予断をはっきりさせることで、自らの認知に注意を促そう。たとえばガマズミの実を子どもが取って食べるのは、おやつとしてであって、大型の果樹の品種導入などによって食用としての利用が駆逐されていった後でも残るのだと。
3.子どもは大人よりはるかに非合理の世界に生きているということ… 子どもは「感覚の世界(養老孟司)」で生きている。子どもの存在そのものの価値を近代社会は否定しつづける。老人の存在も同様。
こうしたことを念頭におきながら、いま40代の母にあたる人たちに残る「摘み草」の記憶をたどってみようと思う。時代でいえば、今から30年〜40年ほど前、1970年〜80年代である。
◉島根県雲南市在住・Aさんの言
島根県川本町で生まれ育ち、小学生の頃に同県頓原へ移住。母は昭和20年生まれ。道の草をとって、こうやって食べるのだと教えられたり、むかごの取り方などを教わった。が、本人は山菜とりなどにあまり興味はない。
〇母のこと
・母は9人兄弟の下から2番目。上の人たちが働きに出るため、10歳頃からご飯をつくる炊事の係をしていた。まわりの人たちから、食べるものについていろんなことを教わった。
・山菜採りが好きだった。春が来るとうれしかったようだ。春になると、車にのせて連れて行ってといわれ、よく出かけた。車を運転していると、ずーっと外を見ていて、「あ、とめて」と言っては、草をとってきていた。
〇教えてもらった草のこと
・道ばたにあったイネ科っぽい、シューっとした葉がある。茎を折るようにしてしゅーっと引き抜くと白い綿みたいなものが出てきて、食べられるということを教えられた。
・味は覚えていない。おいしいとは思わなかったが、まずいとも思わなかった。
〇注:上記の草はおそらくチガヤであろう
※1私たちの脳と心はいまだに、定住農耕よりも、狩猟採集生活への適応をいまだ強く保持している。俗説のようにきこえるが、進化心理学の定見でもある(らしい)。
冬至当夜の日に〜豆腐をつくる・食べる文化の奥にあるもの
「いまでもあそこでは草刈りの後の直会ではひとり豆腐一丁は必ず出すんだそうよ」
「あー、うちもつい最近まではそうだったみたいだよ。さすがに夏の暑い時期に、豆腐一丁はようたべんということでやめになったらしいけど」
今日の茶飲話より。
豆腐はハレの日の食であったことを知らない人もふえてきました。私自身、小さな頃から豆腐は日常の食事でありました。ここ島根県は雲南地域に越してきてから、ハレの日の食として豆腐があったことを知ったのです、遅ればせながら。そして、とりわけこの地域では豆腐をよく食べるし、木綿豆腐の割合が大変に高い。かつてそれぞれの家でつくっていた豆腐の名残が、そういうことをしなくなってからも色濃く残っているからなのでしょう。
そういえばこんな話も80歳を超えたおばあちゃんから聞いたのでした。
「味噌も醤油もつくらんし、こんにゃくもつくらん。豆腐くらいは今でもつくるけど」
全国的にみれば……、どうだろう、味噌をつくる家庭よりははるかに少ないと思いますが。こんにゃくとはいい勝負なくらいでしょうか。一度、可能であれば、悉皆調査をしてみたいものです。漬物や梅干しなどとあわせて。
そして、冒頭にあげた話がでたときに、漂っていた疑問にひとつにちょっとした仮説を出してみたので、今日、はなはだ不備不完全ながら備忘的にあげてみるのです。
《木次ではなぜ豆腐をハレの食とする文化が今に至るまで残存しているのか》
豆腐づくり必要なものを3つあげてみます。
・大豆
・にがり
・石臼(碾き臼)
大豆は日本の食にとってなくてはならないものですし、どこでも栽培できるものですが、牛を飼っていたこの地域では、かなりの量を生産していたのではないかと思います。そう。ここで第1仮説です。
牛の放牧地で栽培するものとして、最後まで残っていたのが大豆なのではないか仮説
わかりますでしょうか?ひとつの長い引用をもって、つづきは、またあらためて加筆します。(なんと、今日は冬至だった! 出雲から伯耆にかけて冬至当夜(トージトヤ)と呼ぶ習俗があります)
石田寛1960,「放牧と垣内」(人文地理12巻2号)より
《仁多郡鳥上地区では垣内すなわち放牧場内に畑(牧畑)があり、夏まや期間中のみに大小豆をつくり、それ以外のときは放牧場となる。
(中略)
「藩政時代には、この一帯の奥山山地を鉄山と呼び、人家に近い山野を腰林といって、2つを区分して利用していたのである。鉄山は鉄山師の支配する山であり、腰林は農民の私的支配下に置かれた柴草山であった。田付山による採草、薪炭諸資材の採取などが自由になされていたのだる。この口鉄山では鉄師の支配権と農民の支配権とが重畳していた。
(中略)
鉄山は林間放牧地であり、それゆえにそれ(畑)は口鉄山でのみ行われるのである。牧野の中にある畑は1年1作であるわけであるが、作物は大豆または小豆に限られる。作付期間は放牧牛のこない時期に限られている。地盤所有者は自己の畑に耕作しながら、その所有権行使は放牧権を侵害しない限りでのみ許されるにすぎない》
(つづく)
詳細ははぶきますが、大豆をつくる山(の畑)だけはたくさんあったということです。
なぜ大豆・小豆に限られるか。
それは牛が夏の暑い間、まや(小屋)にひきあげられるとき(約2ヶ月)をのぞいて栽培できるという条件にみあうものです。それが大豆であったということです。
いや、大豆は60日じゃ無理だろうと。そうなのですが、それなるがゆえに仮説なのですが、牛は大豆が実をつければ口をつけないのです、おそらく。
下の写真は冬至をむかえた我が家の夕食メイン。揚げ出し豆腐でござる。
【雑感と備忘】2017年12月10日〜山を生かす竹林整備研修
2017年12月10日(日)曇りのち雨/10時の気温5℃ 一般1名、学生3名の参加でした。講師は響繁則さん。
◉伐倒講習について
●チェーンソーの目立て
今回あくまで1時間強ほどの簡易なものです。通常の講習ならば午前いっぱいはかかるといいますから、3時間ほどは要するということ。参加人数が少ないこともあり、私自分少し受けてみて、修正の仕方をひとつ覚えられたかと思います。もう使えないだろうなあと見ていたチェーンも、「まだまだ使えるよ」と言われて直す気になりました。ただ、「1時間はかかるんじゃないか」ということ。こんど、じっくり向き合って直します。今週日曜に柵をつくるときにでも。
このような実習を人が出入りするところでやっていると、のぞきにくる人がいます。大変よいことです。チェーンソーを使ったことがある人、使いたい人がのぞきにくるわけです。
1〜2分ほどでも、「ここをこうするんですよ」「昔はこう斜めにと言われていたけど、いまは水平で」「〜〜になっているから」。 こうしたやりとりがあるのはなによりです。
●伐倒実習
チェーンソーもノコギリも基本は同じです。
とくに、斜面では受け口、追い口をつくり、倒す方向を斜面に対して斜めにもっていくこと。そうすることで、危険を回避することと、もうひとつ。その後の作業、すなわち玉切りや移動にかける手数が少なくなります。
やってみてわかるのは、口をつくるときに、重力に対して水平にもっていくことは、ノコギリの場合、とくに難しいということ。この日は用意していませんでしたが、チョークなりで線をひくのがいいということです。こりゃ早速導入です。
口をつくる方向と同時に、つるの幅を左右で変えることでさらに向きをコントロールすることも教わりました。これも加減であって、差がつきすぎると裂けを生じてしまう。
ロープワークはあくまで補助であり、保険であって、ロープの力だけで向きを変えるのではないということが肝要です。
◉雑話について
むしろ、ここのところが、時間をさいて足を運ぶ最大の価値があるところなのですよ、みなさん。
モチキビの話をしたらば、響さんが、いまでもつくっている人を知っていると。 な、な、なんと!
今度おしえてくださいとお願いしました。
竹の焼畑2017-sec.36
12月3日(日)晴れのち曇り 最低気温0℃ 最高気温10℃ 竹の焼畑2017も、なんと、今日で36回目の活動日です。島大里山管理研究会から3名、教員1名+OB1名(午後より)、そして地元の私1名(11時30分〜15時)、計6名での作業でした。
これくらいの気温がいちばん動きやすいので、夏にやるよりははるかにはかどります。今年は雨の日が多い11月でしたが、それでも雨天で中止にする日はありませんでした(小雨の中、やや強行という日はあったにせよ)。それもこれも12月までか。1月に入ると雪で動けなくなる日が出てきますのでね。
◉次年度火入れ地の伐開作業 伐採は進んでいますが、竹の置き方(倒し方・進め方)に難ありで、やはりこの後苦労しそうです。今日の作業ではその点徹底して、成り行きで斜面下に倒すのではなく、横に倒して並べていくという方法で進めています。
この日ははじめてくる3回生が2名いました。来年に向けての希望です。
◉中山の状況その1 さて、私の方では中山の柵づくりと脱穀などを進めました。伐倒した竹を木にかけたりしたために、ひっぱりだすのに息切れ。。。3本ほどを倒して、整理するので1時間ほどかかってしまい、柵の杭をたてるところまでもいたらず。あがった息を整えながら、1月いっぱいにはひとつめの囲いをしあげておきたいなあと、斜面を眺めていました。
温海カブのほうですが、この時期はほんとに日があたらない場所です。とはいえ、2〜3時間ほどは光が入るのではないかと。昨年までの成長ぶりとは趣がことなります。12月に入ったくらいには大きなものができていたのにと。要因は多々ありますが、発芽の悪さが大きい。この場所のカブは火入れ直後にまいていません。蕎麦のために火入れして蕎麦をまいたあと、まったく発芽しなかったところにカブの種をまいているところです。
発芽が悪かったので、なんどか追いまきしています。
くわえて、発芽したものは、かなり虫に葉をくわれています。それも発育の遅さにつながっているでしょう。虫については、9月に火入れしてカブをまいたところでは、さほどみられなかったため、火入れによるなんらかの防虫効果があったのかもしれません。この写真の箇所も火入れをしてはいますが、播種の時期が火入れから数週間たっている。今年のものでいま写真にみえているところは、12月下旬に間引き的にぬいたあとは、すべて種取り用に残す予定です。1年目、2年目がたまたまうまくいったので、気を抜いていましたが、ゆるめてはいかんですね。
◉中山の状況その2 草刈りが入りました。みつけた(復活した)茶の木がばっさり切られていたのは少し残念ですが、下部は残っていて、蕾を新しくつけていました。来年以降、残してふやし、茶摘みをしてみたいものです。冬イチゴもかなり刈り取られましたが、まだ残っており、とっては食べとっては食べして、昼食がわりにしました。
◉蕎麦の脱穀 残りをようやく終えました。結局収量はいくらだっけ? メモが紛失したようで不確かな記憶ですが、1.4kgほどになるのではないかな。1kgはこえているはずで、2kgはありません。さて、蒔いたのはいくらだったのか。量だけでみると蕎麦をつくる意欲をそがれます。
なぜ、焼畑には蕎麦なのか。曖昧なものとはいえ、明治以降の日本の焼畑における作物として、蕎麦はその筆頭にあったことはほぼ確実。出雲地方にあってもそうでありましょうし、出雲蕎麦のルーツにかかわることでもあるので、ここは意欲を駆り立てるものを見つけていきたいものです。
【案内】山を生かす竹林整備研修〜はじめて編
12月10日(日)開催です。
案内文は下段におくとして。なぜやるのかということのメモを自身にあてて置いておくものです。
1. 竹の焼畑事業における伐採技術の向上
大事なことは3つあると思っています。
・道具を大事にする心……手入れを通じて道具を知ること〜モノの特性を知ること〜竹の特性・木それぞれの特性を知ること
・技術を向上させる意思……早く・楽に・なにかのために〜できることがひろがる〜数字(も)大事〜面積・本数
・頭に働いてもらう条件づけ……頭を使わない社会の中、山を生かすのは人を生かすこと〜「頭使って!」といっても使ってもらえない〜自分と家族(仲間)に対してどう言葉を発するか
2. 竹の焼畑事業における賛同者・協力者・自分の山でやってみたい人を募る
【案内〜山を生かす竹林整備研修_2017年12月10日】
これからはじめたい! どうしたらいいの? そんな初心者向けの実践的研修会です。響繁則さん(国土緑化推進機構選定 森の名手・名人)を講師に、荒廃竹林整備の基本的な考え方と注意点。伐倒講習・搬出等作業の実際を行います。また、チェーンソー使用者には別途講習を行います(※注1)。天候や参加人数の状況に応じて消し炭づくりなどもあり。
はじめての理論編は希望者あれば1月に開催予定。
◉お申込・お問い合わせ先
面代真樹
森と畑と牛とホームページのフォームをご利用ください。
【要項】
◉日時
12月12日(日)
9:00〜14:30
※午前のみ参加も可
※遠方からこられる方、チェーンソーを使わない方は、10時からの参加でも可(9時〜10時はチェーンソー講習か、のこぎり・鉈の使い方講習等を実施)
◉実施場所:奥出雲町布勢地区内竹林
ダムの見える牧場の牛舎前に9:00集合
◉定員:15名までを予定
◉参加費:700円(保険・資料代として)
※島根大学学生は無料(ただし条件があります。お問合せください)
◉持ち物
・のこぎりとなた(お貸しすることもできます)
・作業用手袋(革手袋推奨。厚手の軍手等でも可)
・山に入れる服装と靴で(斜面ですべらないスパイクかミゾのある作業靴等)
・防寒のための服装
・昼食弁当、飲み物
※注1. チェーンソー使用者はチャップス(お持ちでない場合はお問い合わせください)
◉荒天(大雪等)の場合中止とします。
◉以下3団体の共催です
奥出雲山村塾
森と畑と牛と
竹の焼畑2017―sec.35
11月25日(土)曇り 気温10℃(11時頃)
島根大学里山管理研究会。停滞していた竹林伐開活動が10月に入ってから活発化しています。この日は5名が参加。複数回参加するメンバーが少なく、熟練がすすまないのが、変わらぬ悩みです。

人海パワーで突破ということですね。
伐倒する人は、これを斜面に並べて積む人とは別な人になります。無駄とはいえないまでも、これでは切ったものを下に移動した後に玉切りし、また上にあげるしかありません。
1〜3本切るごとに積むようにしたほうが、数倍効率的であるはず。あるいはこうして切り倒すのであれば、斜面では焼かずに下ろした竹材は下で焼いて炭にしてしまうというのも一計か。
ここは口出し無用と心得、中山での柵作りを少しでも前に進めておきましょうぞ。 とはいえ、この日は麦踏みだけして引き上げました。

山を下りる途中、なんと、茶の木を発見。
栽培していたものから、種がこぼれて、ここで生き続けいたのか。種をとってひろげてみるのも一興と思いついた次第。
次回の活動日は、12月3日(日)です。