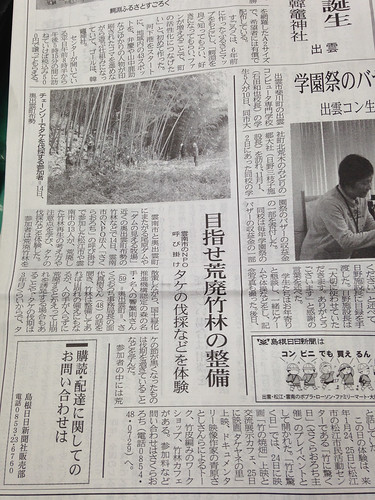2025/08/12現在。多少の補筆をする。
以下は2015年2月に書いたもので、引用したところには誤りも多いのだが、そのままとするが、特に気になる1点について。
*1「江戸時代末期になると,自然に菌が付着するのを待つのでなく,積極的に種菌を植えつける方法が開発され, 椎茸栽培は大分県内に広まり」とあるが、まず、積極的に種菌を植えつける方法が試みとして始まったのは昭和初期。ひろまったのは戦後である。椎茸栽培の初期的広まりは大分県内に限らない。宮崎、鹿児島、三重、和歌山、静岡(伊豆)、複数にわたる。大分に発してそこから全国へというように、この津久見の発祥地をたてた人たちに思えたのにも理由があろう。
〜〜以下元〜〜〜
備忘として記すものなり。
それは「タヌギなどの原木に鉈で傷をつけ(鉈目という)、自然界に浮遊しているしいたけ胞子が鉈目に付着するのを待つという極めて原始的な方法です」とある。
私にとって、鉈目法についての関心は、いま、できる人はいるのか、が真ん中にある。
映画「千年の一滴」の中では、宮崎県椎葉村の椎葉クニ子さんをあげていた。
山の谷ごとに異なるような微細気候(マイクロクライメット)の読み方という点で、いま取り組んでいる竹の焼畑の可能性ともつながる。
web辞書どまりの記述では、傷をつけて待つという、のんびりしたものだが、私が聞いたことがあるのは、胞子が飛んで付着する時期を長期で読みながら準備し、短期でよむその数日の間に、一気に原木を運ぶ(水から出す? 鉈目をいれる? それら全部?)のだというようなこと。
文献レベルでもう少し知る必要がある。
大分がその発祥の地とされる証左はこちら。
http://hamadayori.com/hass-col/agri/SiitakeSaibai.htm
なくなるといけないので、複写しておく。
日本特殊産業椎茸栽培業者発祥地
大分県津久見市上宮本町
JR日豊本線の津久見駅から 500mほど南西に 浄土宗の寺・長泉寺がある。
寺の土塀外側の道路脇に,古い苔の生えた大きな石碑と「由来記」と書かれた副碑が建っている。
大分県は 椎茸の大生産地で,乾椎茸では 全国で第一位,30%のシェアを有する。栽培の歴史も古く, 江戸時代初期(17世紀前半)に豊後の国で炭焼きをしていた源兵衛という人物が, 原木の残材に椎茸が生えるのを観察して 初歩的な人工栽培を始めていたという。
これは“鉈目法”と呼ばれる方法で,クヌギなどの原木に鉈で傷をつけて野外に放置し,自然に椎茸菌が 付着して繁殖するのを待つという原始的な方法であった。
江戸時代末期になると,自然に菌が付着するのを待つのでなく,積極的に種菌を植えつける方法が開発され, 椎茸栽培は大分県内に広まり,明治以降は椎茸輸出の増加に伴い生産量も急増した。
大正時代になると,種菌を原木に打ち込む“埋ほだ法”が開発され, さらに昭和になるとくさび型の木片に椎茸菌を培養した“こま菌”を原木に打ち込む方式がが開発されて, 簡便な接種方法のため広く受け入れられ全国に普及した。
この発祥碑は,江戸時代末期に種菌を人為的に植えつける方法が行われるようになったことを記念・顕彰したもので,昭和30年に建碑された。
また,内陸の豊後大野市には「しいたけ発祥の地」という碑が建っている。
現在国内で栽培されている椎茸のうち上記のような“原木”を用いる方法を採っているのは少なくなり, 多くは“菌床法”と呼ばれる,おが屑に栄養分を混ぜ込んで固めた“菌床”で種菌を培養したもので 栽培されるようになっている。 しかし大分県での椎茸栽培は,現在もほとんどが原木を用いているのが特徴である。
なお,この発祥碑については 若干の疑問点がある。
§ 発祥碑の表面に刻まれている文字は「日本特殊産椎茸栽培業者発祥地」と読み取れ, 「産業」の「業」の文字が抜け落ちているように思われる。
「特殊産」では意味が通じないし,副碑(由来記)には 「日本特殊産業椎茸栽培業発祥之地」と書かれていることから,「特殊産」というのは誤記ではないかと想像される。
§ 標題の「日本特殊産業」とは何を意味するのだろうか? 椎茸栽培は林業に分類されているので,その中の“特殊”な業態という意味であろうか。
§ 椎茸栽培の発祥地は “静岡県の伊豆半島”説がある。
伊豆は17世紀末~17世紀にかけての話であるのに対して,大分県は 17世紀前半なので, 大分の方が若干早かったが,いずれも不確かな伝承に基づくので断定は難しい。
日本特殊産椎茸栽培業者発祥地
(副碑)
由来記
往昔天保の頃津久見の先覚者彦之内区三平西之内区徳蔵嘉吉平九郎
久吉等の椎茸栽培業研修に端を発し三平徳蔵は石見へ出向椎茸栽培
業を経営す是中国に於ける専門事業者の始祖なり嘉吉平九郎久吉は
九州奥地に於て創業した是九州地方の専門的事業者の始祖にて郷土
の子弟に是を継続して連綿百二十余年伝統を保つ而て本業の推移は
時恰も幕末期にて営業上幾多の支障あり従て労多く得少く継続困難
の状態なりしが明治初年日支貿易開港以来輸出椎茸旺盛となり価格
の躍進につれ本格的に事業化し此頃より業者の数も著く増加せしは
歴史が明示する九州地方百九十四名中国四国済州島地方七十余名の
専門事業者を算す斯くて日本特殊生産品として輸出市場に名声を高
揚し神戸港及長崎港を経由輸出椎茸は年々巨額に達せり其大部分は
津久見人の出先経営地の生産品である実に開港以来七十余年間何等
名聞も求めず深山に籠り孜々黙々として外貨獲得の一役を果し其余
沢は郷土の経済安定に寄与し一面着々未墾地の開拓を励行し風土に
最も適応した柑橘園の基礎を構築したのも現実が証する此先輩の貴
い伝統を子弟は能く継承し出ては貿易品増産に勤め入りては郷土の
産業を振興した其業績の偉大さは全国的に総合し椎茸栽培専門業者
として抜群的特技の存在にて是業界再興の権威日本特殊産業椎茸栽
培業者発祥之地を穣成す此国家的大産業の振興は津久見市の大なる
誇なり茲に碑を建設し過去と現時を通じ斯業に精進せる郷土人士の
敢闘精神と其業績を讃へ以て永遠不朽の記念とす
昭和三十年五月二十一日
一介茸山子 西郷武十 (八三翁)
そして、大分から中国地方へこの技術が伝わる拠点となったのが、匹見町広見であるという。それについては今度。

 径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。
径」すなわち石見の枕詞が冠されている。桑原良敏は『西中国山地』(1982,渓水社)の「広見山」の項で、まず吉田茂樹『日本語源地名辞典』をひきながら、ヒロミは広(ヒロ)に接尾語ミを付加したもので、「山地の中で部分的に広くなった平地のある所」だということを広見河内の地形がまさにそれであると、述べている。桑原は「広見山」のことをここで述べており、吉田の説明をいったんは受け入れ、広見山とは広見という村の奥にある山という命名由来とするのが穏当であろうとする。しかし続けて、広見山は広く見渡すことのできる山という意味にもとれると述べ、広見山と並ぶ十方山もそうであると、双方ともに頂上部の植生が笹となっていて、四方を見渡すことができるのだと。そうしたことは登った経験をその時の実感を重視するものであろう。他の山名にもそうした感覚が生かされた名になっているものがあるのだと考える。ひとつの見方として心に留め置きたい。広見(村名)よりも広見山(山名)が先にあるという名語史は『石見八重葎』も併記している。「又廣見山有故共云」と。