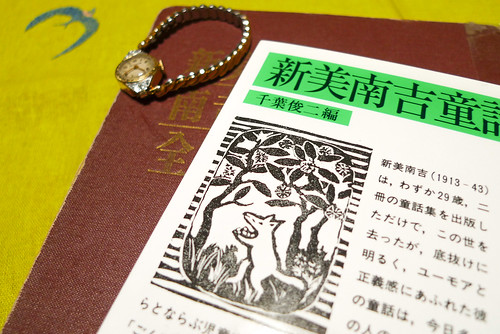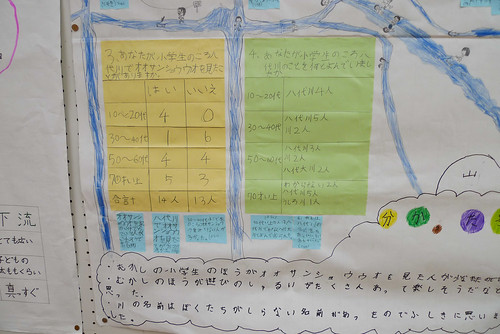記事タイトルであげたトークライブのお知らせです。
◉主 催:ナレッジ・ロフト「本とスパイス」&カフェ・オリゼ
◉日 時:1月27日(金)
開 場…18:30
トーク…19:00〜20:20(20:30〜22:00 食事)
◉場 所:カフェオリゼ(木次町里方)
◉参加費:2,500円(スリランカカレー/ドリンクセット含)
◉定 員:12名
◉申 込:「大人のためのごんぎつね」参加希望として、下記のメールアドレスまでお名前とご連絡先をお知らせください。返信のメールをもって受付終了とさせていただきます。メールはこちらまで anaomoshiro★gmail.com(★⇒@)
◉内 容
「本とスパイス」提供の、月刊ペースで1冊の本を巡るトークライブ。第2回目となるお話は、大人のための「ごんぎつね」です。
国語の教科書に採用されて以来、6000万人が読んだといわれる「ごん狐」ですが、同人誌「赤い鳥」に発表されたのは昭和7年、満州事変の翌年であり、著者、新見南吉19歳の時でした。
南吉の童話作品の大半は発表されることなく、29歳と8ヶ月で没する数年間に故郷で書かれたものです。千葉俊二編「新見南吉童話集」の中から、遺作となった「狐」、「牛をつないだ椿の木」を読みながら、ごんぎつねと共通する南吉の世界に迫ります。
さて、ごんぎつねには3つの原稿が存在します。
広く読み知らされた「ごん狐」は、新見南吉の原稿に、鈴木三重吉が手を入れたものであります。従来、研究者の間では、三重吉が手を入れたことで「ごん狐」は名作となったとされてきました。しかし近年、「いや、それ違うんじゃないの」との読み方が出てきています。私も同様に考えます。そして、ごん狐には、南吉が郷里の半田市(愛知県)で伝承として聞いた「聞き書き版」が存在していました。
ごんぎつねには3つの異なったバージョンがあるのです。とりわけ、物語の結末が、決定的に異なるのです。数文字の違いであり、オリジナル版の不自然さの中にこそある真実があったのだとすれば…………。
「ごん、お前だったのか」
そう、誰もが覚えているこの言葉の後です。
戦争で失われたのは人の命だけではありません。滅んでいったものがたくさんあり(い)ます。南吉は、童話としての完成度よりも、失われていくものの真実=物語をこの世に残したかったのです。それがなんだったのか。銃に撃たれたごんの願いとともに、物語の奥へと、たどっていきたいと思います。
◉
今回のお話は、キツネ、オオカミ、ウマ、ウシ、クマ、サル、あるいはカッパやオロチ……、私たちの身近にいた生き物との関係を、信仰と民俗と物語=童話、を通じて探っていくものです。また、編集者として作家の原稿をどう読むのかという関係性をも考えながら、読み解いていきます。