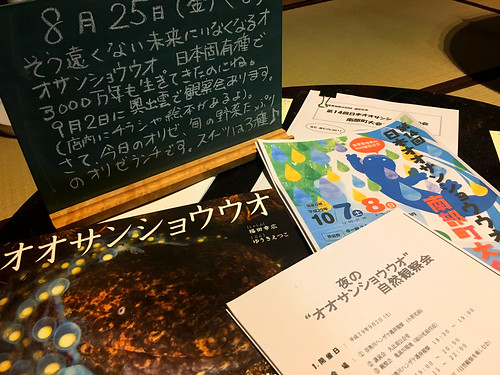9月8日(金)快晴。最高気温27℃。 活動報告です。
○参加者:島大から2名、教員1名(午後〜)、地元1名の計4名。
○時間:10時~16時
○内容
10:00~10:20…作業内容協議、確認。
10:30~12:15…火入れ地草刈り整備
12:20~13:10…昼食・休憩
13:15~14:40…火入れ地草刈り整備、8月夏焼地と中山雑穀地観察&ニンジン播種
14:50~15:50…春焼地のさつまいも救出(草刈)/ホンリー間引き/アワ、ヒエ栽培地観察

▲この草を刈り。見えないですが、草の下に竹がうまってます。 ○課題 年度当初からではあるが、活動参加者の見込が計画より相当に少なく、半分以下ではなかろうか。規模をおさえた計画とあわせて、技能向上を次年度からははかりたい。夏焼は9月に雑草灌木等を燃やすことにして、他地域への研修旅行を企画するのがよかろう。
◉栽培地状況 ○蕎麦は花をつけています。
○カブ、3日ほど続いた降雨で発芽です。一安心。

○中山袖地のアマランサスはまずまずの出来(2年畑) 
○中山そば地跡はここにきて牛に食われてしまいました。アマランサスが多少収穫できる程度か。 ・アマランサスは葉を食べます。茎は細ければ食べる。いちばんよく食べるのは大豆。花をつける前にほぼ全滅。モチアワも実は食べないのですが、茎と葉を食べるので踏み倒すなどされており、熟す前に倒伏。もともと発芽・生育ともによくなかったのですが、ここへきてほぼ全滅の様相です。

○春焼地のホンリーが色づいてきました。美しい。