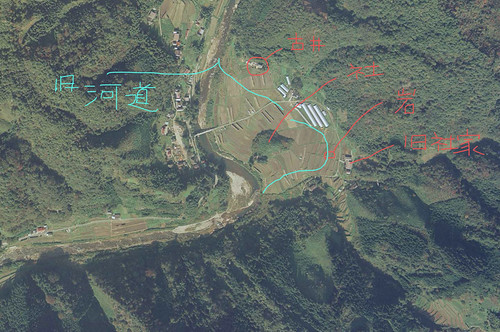梅雨らしい雨が続いています。昨日奈良から帰り、春焼き畑地の間引きにでかけました。
●アワ、アマランサス、ヒエ
アワはかたまっているところを多少抜き取った程度です。あと10日くらいたったころに手をつけても遅くはないでしょう、たぶん。
問題はアマランサスです。発芽はよくなかったのですが、おそらくここ数日で芽を出しているものがちらほらとありました。1ヶ月近くたっての発芽です。
追加で種蒔きしようと、少しばかりあまっていた種をもってきていたのですが、やめにしました。うまく土ごとほりとって、移植できないかな〜。5つ6つやってみました。明日もひきつづきやってみようと思います。
雨が降っていたので、写真はとっていませんが、急に大きくなってきていますよ、アマランサス。2メートルを超えるらしいので、ひまわり並だと思えば、順当な成長でありましょうぞ。
そして、ヒエをどうしましょうかと。筋まきしたのが混みすぎているので、間引きは必須なのですが、これもうつせればうつしたいし、できるのでは?と。
明日、雨が降らなければ、杉を倒して下のほうに植えてみたいものです。
●再生竹
かなり伐りました。大小あわせて50本はやっつけたと思います。
●クズ
20メートルはのばしてものがあったので、5カ所くらいの根元をざっくりと伐りましたが、何度かやんないといかんのでしょうね。
●トマト
先週とさほど変わりはないように見えます。
●サツマイモ
同上。
●大豆
順調にのびてきています。