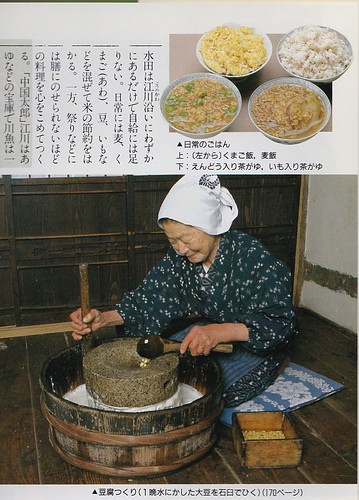※facebookのノートにまとめていたのだが、編集のしづらさにしびれをきらし、移転することにした。
・きっかけ1)「6年続けて同じお客さんを案内していて、もう行くところがない。どこかない?」と聞かれたが、こたえる間がなかった。→例)神名火山(野)をめぐればどうでしょう。万九千神社の古地である斐伊川河川の中から仏教山を仰ぎみつつ、山麓の古社を訪れるということか。雲南市であれば神原神社。松江であれば大庭の神魂神社、雑賀の売豆神社紀神社、朝酌の多賀神社。それぞれ本殿ではなく、その周辺をあたるのがよろしいかと。出雲大社でも佐田神社でも神迎祭りの斎場は本殿ではない。むしろ関係を絶っているとでもみたほうが、おもしろくなります。
・きっかけ2)「江戸時代に大社の御師がひろめたデマだろうに」という方がいらしたが、これも、ちょっと一言はさむ間もなかった。→気持はわかりますけどね。江戸のベストセラー「広益俗説弁」にも「地元出雲では神有月なんてだれも言ってませんよ」と一刀両断ですものね。とはいえ、ほつれた糸をほぐすのは骨が折れます。まずは基本をおさらい。
1.神無月の語源
藤原清輔『奥義抄』〔1135〜44頃〕上「十月 神無月 天の下のもろもろの神、出雲国にゆきてこの国に神なき故に、かみなし月といふをあやまれり」
…………これを第一にとる場合が多いのであるが、ほかに以下あり。大日本国語辞典より
(2)諸社に祭のない月であるからか〔徒然草・白石先生紳書〕。
(3)陰神崩御の月であるから〔世諺問答・類聚名物考〕。
(4)カミナヅキ(雷無月)の意〔語意考・類聚名物考・年山紀聞〕。
(5)カミナヅキ(上無月)の義〔和爾雅・類聚名物考・滑稽雑談・北窓瑣談・古今要覧稿〕。
(6)カミナヅキ(神甞月)の義〔南留別志・黄昏随筆・和訓栞・日本古語大辞典=松岡静雄〕。
(7)新穀で酒を醸すことから、カミナシヅキ(醸成月)の義〔嚶々筆語・大言海〕。
(8)カリネヅキ(刈稲月)の義〔兎園小説外集〕。
(9)カはキハ(黄葉)の反。ミナは皆の意。黄葉皆月の義〔名語記〕。
(10)ナにはナ(無)の意はない。神ノ月の意〔万葉集類林・東雅〕。
(11)一年を二つに分ける考え方があり、ミナヅキ(六月)に対していま一度のミナヅキ、すなわち年末に近いミナヅキ、カミ(上)のミナヅキという意からカミナヅキと称された〔霜及び霜月=折口信夫〕。
「陰神崩御の月」というのは、なかなかにおもしろく、クリスマスのルーツともかかわってくるところか。古事類苑の中では、もっとも字数をさいている説である。
◉1,056ページ冒頭部。ここをきちんとふまえておかないといけない。すなわち、
他国でも「神が村を出て行く」ということはいつの頃からかあったことだが、「出雲へ行く」ということになったのは、文献上では鎌倉時代以降のこと。地元出雲で「おいでになる」となったのは、昭和に入ってからか?
・平安時代後期〜鎌倉時代……藤原清輔『奥義抄』の時代がほぼ初出といえるようだが、時代とともにふえる。出雲大社へ行くとはまったく出てこない。「出雲へ」である。
・南北朝の中頃から……はじめて具体的な社名が出てくる。出雲大社ではなく佐太神社。
・戦国時代に突如、「出雲大社へ行く」となる。。
参照『日本紀 神代抄』
・以降、佐太神社より出雲大社へという記述が多くなる。が、しかし、地元伝承は別。
さて、他国でどうであったかであるけれど、餅つきや村境での葬送儀礼があった。これについては、また改めて。
◉参考資料……大日本国語辞典【解説・用例】より
〔名〕(「な」は「の」の意で、「神の月」すなわち、神祭りの月の意か。俗説には、全国の神々が出雲大社に集まって、諸国が「神無しになる月」だからという)
陰暦一〇月のこと。かんなづき。かみなしづき。かみなかりづき。《季・冬》
*万葉集〔8C後〕八・一五九〇「十月(かみなづき)しぐれにあへる黄葉(もみちば)の吹かば散りなむ風のまにまに〈大伴池主〉」
*古今和歌集〔905〜914〕雑体・一〇一〇「きみがさすみかさの山のもみぢばのいろ かみな月しぐれの雨のそめるなりけり〈紀貫之〉」
*蜻蛉日記〔974頃〕下・天祿三年「かみな月、例の年よりもしぐれがちなる心なり」
*曾丹集〔11C初か〕「なにごともゆきていのらんと思ひしを社(やしろ)はありてかみな月かな」
*色葉字類抄〔1177〜81〕「十月 カミナツキ」
*名語記〔1275〕一〇「十月をかみな月となづく、如何。これは、日本国の諸神たち、御まつりごとのために、出雲のいつきの宮へあつまり給て、都城には、かみいませずとて、公家にも御神事を、をこなはれざれば、神無月といふと、ふるく尺しをける也。この説、勿論歟」
*徒然草〔1331頃〕二〇二「十月を神無月と云ひて、神事に憚るべきよしは、記したる物なし」
*日葡辞書〔1603〜04〕「Caminazzuqi (カミナヅキ)。歌語。ジュウガチ」
ーー以上